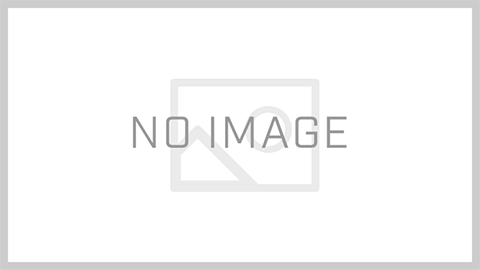新年の風物詩として毎年お正月に行われる「マグロの初競り」
新年の風物詩として、毎年お正月に行われる「マグロの初競り」。全国各地のニュースで取り上げられるため、毎回その落札価格が注目を集めます。毎年、数千万円、時には億を超える金額で落札されることもありますが、これを聞いて「こんな高額で買ったら、利益を出すのは無理じゃないか?」と思う方も多いかもしれません。
実際、通常の卸価格では1万円程度/キロのマグロが、初競りでは数十倍もの金額で落札されることが多いです。しかし、落札者は本当に赤字になってしまうのでしょうか?それとも、何か別の理由があるのでしょうか?
今回は、「マグロの初競り」の仕組みと、それに関わる企業がどのように利益を生み出しているのかを掘り下げてみましょう。
効果1. 宣伝効果
まず最初に挙げられるのは、宣伝効果です。マグロの初競りは、毎年全国のメディアで取り上げられる大きなイベントです。特にテレビでは、競りの様子が大々的に放送されます。この放送が、企業にとっては計り知れないほどの価値を持つ宣伝効果を生むのです。
テレビCMを使って宣伝しようとすると、製作費や放映費が必要で、最低でも500万円以上はかかると言われています。例えば、地上波テレビ局127社で全国放送されると仮定すると、500万円×127社=6億3千5百万円。これだけで、1回の放送のためにかかる費用が6億円を超える計算になります。 これに対して、マグロの初競りは、放送費用がほぼゼロで、全国規模で取り上げられます。連日放送されるため、その効果は絶大。もし、今年の競りで落札額が2億700万円であったとしても、この宣伝効果を考慮すれば十分にその価値は超えていると言えるのです。(テレビ局の数字は、2021年度末集計:出典:総務省|令和4年版 情報通信白書|)
効果2. ブランド力アップ
次に挙げられるのは、ブランド力のアップです。テレビCMは、あくまで「企業側が一方的に宣伝したい商品を押し出す」形になります。一方で、マグロの初競りは、メディアがその企業や商品を客観的に取り上げる形で放送されます。これにより、企業は「信頼のある存在」として評価され、ブランド力が向上します。
さらに、お正月にマグロの初競りで高額な落札を行うこと自体が、縁起の良い行動として捉えられることもあります。消費者は「良質なものを仕入れ、提供できる企業」という印象を持ちやすく、これが企業のイメージアップに繋がります。
加えて、現代ではSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じた情報拡散が急速に進んでいます。これにより、競りの様子やその企業が行った取り組みが、さらに多くの人々に伝播し、さらなる宣伝効果を生むことになります。
効果3. 投資と見なす企業
また、マグロの初競りに参加する企業は、単に利益を追求するのではなく、投資活動として捉えていることが多いです。高額で落札されたマグロが直接的な利益に繋がらない場合でも、その後の企業イメージやブランディングにおいては大きなリターンを見込んでいるのです。
特に高級志向の強い消費者層をターゲットとする企業にとって、初競りでの参加は有効なマーケティング戦略の一環となります。高額なマグロを「手に入れることができた」という事実自体が、信頼性の証として機能し、その後の商業活動において高い効果を発揮することが期待されます。
効果4. 競り後の販売価格
もちろん、マグロの初競りで落札されたマグロはその後も流通市場で販売されますが、販売価格自体は必ずしも初競りの落札価格と一致しません。初競りでの高額落札は、あくまでそのイベントの注目度や、ブランド価値向上のための投資の一環として理解されるべきです。競り後、消費者に提供されるマグロが高級品であることは間違いなく、これが「高価格帯商品」として、付加価値を生むことになります。
例えば、高級寿司店や高級料亭では、初競りで手に入れたマグロを一流の料理として提供することで、客単価を高め、店舗のブランドイメージを向上させる効果が期待できます。
結論
以上のように、マグロの初競りでの高額落札は、一見すると企業にとって大きな赤字を生むように思えるかもしれません。しかし、実際には宣伝効果やブランド力の向上、さらにはマーケティング戦略の一環として、大きなリターンを得るための投資活動と捉えることができます。
これらの要素を総合的に見ると、単純に「仕入れコスト」として考えるのではなく、企業価値の向上や宣伝活動の成果として、落札金額以上の効果を得ていることがわかります。そのため、初競りでの高額落札が赤字ではなく、企業にとっては戦略的な投資であることを理解することが大切です。 次回のお正月、テレビやSNSでまた盛り上がるマグロの初競りを見かけた際には、その背後にある企業戦略にも思いを馳せてみてください。